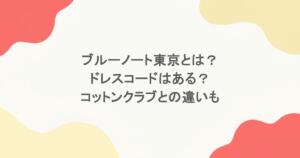よく耳にすることわざでも、正確な意味はよく分からないなんてこと、よくありますよね。例えば「馬の耳に念仏」、皆さんは正しい意味を理解していますか?
今回はことわざ「馬の耳に念仏」について紹介します。
「馬の耳に念仏」とは
馬の耳に念仏 は「何か注意されたり意見を言われたりしても、全く聞く耳を持たないので全然効き目がない」という意味のことわざです。二度、三度と同じ失敗をしている人に次は失敗しないように注意すべきポイントを教えても、その相手はアドバイスに全然耳を貸さないので結局また同じ失敗をしてしまう、といった時に「あの人に注意しても馬の耳に念仏だよ」と使える言葉ですね。なお、目上の人には使えない言葉である点に注意が必要です。
「馬の耳に念仏」のルーツは?
では、どうしてそういった状況を表す言葉として「馬の耳に念仏」が誕生したのでしょうか。確かに馬の耳元で念仏のようなありがたい言葉を話しても馬は何も理解できないので意味はないですよね。でもそれは馬に限らず、人間以外の動物なら何でも良かったはずです。
馬の耳に念仏ということわざには元となった言葉があり、それが「馬耳東風」。馬耳東風も「他人からの注意や批評を聞いても受け入れることなく、全て聞き流すこと」を意味する四字熟語です。馬の耳に念仏の元となった言葉だけあって、意味がとても似ていますね。
「馬耳東風」のルーツは?
となると気になるのは馬耳東風のルーツです。馬耳東風は中国の詩人、李白の詩が元となった言葉です。李白の「答王十二塞夜独有懐」という詩の中に「世人之を聞けば皆頭を掉り、東風の馬耳を射るが如き有り」という部分があり、これが「世の人達は頭を振って聞き入れない。まるで春風が馬の耳に吹くようなものである」という意味になるのです。
どんなに良い詩を読んでもそれが理解できない人は認めようとしないということを嘆いた李白。その嘆きの一節が後に四字熟語やことわざになったのです。
李白が世の人々を馬に例えた
「なぜ馬なのか」という謎の答えは、そもそも李白が最初に人々を馬に例えたからなのですね。てっきり馬が登場する昔話が元になっているのかと思ったのですが、実際は最初から例えの話だったというわけです。
馬は遥か昔から人と共に生きた動物で、移動手段などとして昔の人々には馴染み深い存在だったことでしょう。ですが、それ故に馬に言葉が通じないことのもどかしさなども人々は感じていたことでしょう。李白の例えに馬が出てくるのも必然だったのかもしれませんね。
「馬の耳に念仏」と似た言葉は?
馬の耳に念仏には似た言葉が多数あります。例えば「犬に論語」「兎に祭文」「牛に経文」などです。どれもことわざのつくりとしては馬の耳に念仏と同じ、「動物にありがたい言葉」というつくりになっていますね。「動物なら馬でもなんでもいい」というのは当にその通りだったという訳です。
「猫に小判」や「豚に真珠」は」?
私達に馴染み深いことわざとしては「猫に小判」や「豚に真珠」もありますよね。これらは「値打ちが分からず役に経たないこと」をあらわすことわざなのですが、考えてみると馬の耳に念仏などと同じつくりになっているように思えます。「馬の耳に念仏」も「猫に小判」も「動物」と「ありがたいもの」の組み合わせですからね。
言葉か物かという違いがあり、微妙に使える場面に違いは出てくるような気もしますが、おおまかなにはこれらの言葉の意味は同じです。ちなみに「牛に説法馬に銭」や「犬に念仏猫に経」など、動物を二種使った贅沢なことわざもあるようですよ。意味はそう変わらないんですけどね。
ことわざ一覧(五十音順) – ことわざ・慣用句の百科事典 (proverb-encyclopedia.com)
最後に
今回は馬の耳に念仏の意味や似たことわざについて紹介しました。なお「馬耳東風」から「馬の耳に念仏」に派生する過程の中には「馬の耳に風」という慣用句もあったようです。なんの意味もないことを「馬の耳に風が吹くのと同じ」と表現した李白の感性、面白いですよね。似たように、何かをする際の無駄な努力を表すことわざとして「猫の首に鈴をつける」もありますよ。